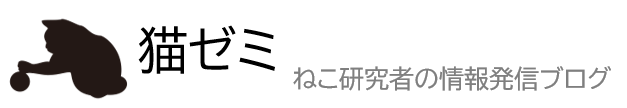【ねこの研究者】永澤巧– Author –
【ねこの研究者】永澤巧
-

猫と飼い主の爪ホルモン調査【募集ページ】
お時間をいただき、誠にありがとうございます。 研究の目的 本研究室では、猫と飼い主の双方が、健康で長生きするための方法を日々探っております。 今回の調査では、猫と飼い主の爪から、中長期的な健康状態(ストレスホルモン)を測ります。 同時に、飼... -

猫との暮らしインタビュー調査【募集ページ】
研究の目的 本研究室では、猫と飼い主の双方が、健康で長生きするための方法を日々探っております。 そのためには、猫の飼い主が、普段の猫との暮らしで何を考え、どんな思考をしているのかを知ることが非常に重要です。 そこで今回の調査では、猫の飼い主... -

ペット愛着度尺度
自身が一緒に暮らしているペットを想像しながら、以下の23問の質問に回答してみてください。回答の仕方は、以下の4種類です。 【回答の選択肢】0点 全くそう思わない1点 そう思わない2点 そう思う3点 とてもそう思う 【問題文】 私にとって、ペットは友達... -

2023年の振り返り・2024年の抱負
2023年の振り返り 1~2月 Amazonの倉庫でのバイトをつづけていました。いい職場でしたが、予定よりも早くアルバイト期間が打ち切られてしまい、別の単発の仕事もしていました。研究の仕事がしたいけれど見つからない、、。 また、リバネス助成金プログラム... -

2022年の振り返り・2023年の抱負
2022年も色々ありました。何したかな~と、ちょっと振り返ってみます。 2022年の振り返り 1月 博士論文の口頭発表がありました。 おそらく前代未聞ですが、完全にリモートで、ZOOMを介して行いました。 私の家族がコロナに感染し、私が濃厚接触者になった...