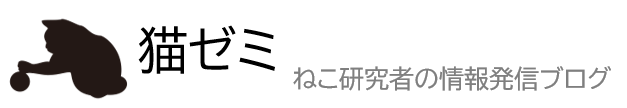本日の輪読会は5題でした。
~~(=^・・^=)~~
題目1「Social referencing and cat–human communication」
I. Merola, M. Lazzaroni, S. Marshall-Pescini, E. Prato-Previde
Anim Cogn (2015) 18:639–648
DOI 10.1007/s10071-014-0832-2
目的:
猫が人間に対して社会的参照(意思決定や行動選択を、周りの反応をもとに行うこと)をするのかどうかを検証すること。
方法:
扇風機(恐怖刺激)と猫が対面する場面を設定し、人がその扇風機に対して『ポジティブな反応』を示す場合と『ネガティブな反応』を表現した際に、猫がその後の行動を変化させるかどうかを行動観察した。
結果:
人の反応の仕方によって、猫は行動を変化させた(人がネガティブな反応を示した時の方が、猫は素早く動く、など)!しかし、社会的参照とまでは断定できない。
虎太郎所感:
恐怖刺激の設定が、以前の犬の研究を参照しているため、適切だったかは難しいところですね。
題目2「Does social participation reduce the risk of functional disability among older adults in
China? A survival analysis sing the 2005– 2011 waves of the CLHLS data」
Min Gao, Zhihong Sa, Yanyu Li, Weijun Zhang, Donghua Tian, Shengfa Zhang and Linni Gu
Gao et al. BMC Geriatrics (2018) 18:224
https://doi.org/10.1186/s12877-018-0903-3
目的:
中国の高齢者の社会参加と、機能障害の発症に関連性はあるかを確認すること。
方法:
大規模なアンケート調査。サンプル数は104,468人。
結果:
ボランティアに参加するなどの組織的な社会参加や、マージャンなどの余暇活動のような社会参加、どちらも機能傷害のリスクを低減することが示された。
虎太郎所感:
非常に大規模な研究なので、信頼性が高いデータのように思います。日々、他者とのかかわりを何らかの形でも持っておくことは、健康を保つための秘訣だと言えます。
題目3「Inducing resistance to the misinformation effect by means of reinforced self-affirmation: The importance of positive feedback」
Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk
PLoS ONE 14(1): e0210987.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.021098
January 22, 2019
目的:
自身の発言や意見に自信を持つための方法に、RSA(reinforced self-affirmation)がある。この方法にはいくつか種類があり、どのやり方が最も有効であるかを検証すること
方法:
記憶力に対してフィードバックをおこなう『Memory-RSA』と、知覚能力に対してフィードバックをおこなう『Perception-RSA』を行い、比較する。
結果:
すべてのタイプにおいて、効果的であることが示され、記憶力だけではなく知覚能力に対してフィードバックすることも効果があるようです。
虎太郎所感:
実験が複雑かつ、研究の本質がつかみづらい論文でした。他者からの意見によって自身の意見が左右されるというのは、いい面もあり、悪い面もあるように感じました。
題目4「Associations between seasonal temperature and dementia-associated hospitalizations in New England」
Yaguang Wei, Yan Wang, Cheng-Kuan Lin, Kanhua Yin, Jiabei Yang, Liuhua Shi, Longxiang Li, Antonella Zanobettia, Joel D. Schwartz
Environment International 126 (2019) 228–233
目的:
認知症の有病率と、気温の関係性を探ること。
方法:
2001年から2011年の期間における、ニューイングランド州在住の65歳以上の3,069,816名へのアンケート調査。
結果:
夏季の平均気温が1.5℃上昇することは、認知症による病院への入居率を12%上昇させていることがわかった。
虎太郎所感:
気温と認知症の関係、というアプローチが、私にとって非常にユニークなものであると感じました。地球温暖化とも絡めれば、違った形の啓発活動につながるのではないかと思います。
題目5「Dog owners are more likely to meet physical activity guidelines than people without a dog: An investigation of the association between dog ownership and physical activity levels in a UK community」
CarriWestgarth, Robert M. Christley, Christopher Jewell, Alexander J.German, Lynne M. Boddy & Hayley E. Christian
Scientific Reports | (2019) 9:5704 | https://doi.org/10.1038/s41598-019-41254-6
目的:
犬との散歩は、「その他の身体活動」の代わりになっているのかどうかを調査すること。
方法:
385世帯694人に対するアンケート調査。
結果:
犬を飼育している人のほうが、ウォーキングの時間が長く、頻度も多いことが分かった。
虎太郎所感:
犬を飼育している人が健康である要因は、やはり身体的な活動の量を増加させる点にあるのでしょう。
題目6「Validation of the Visual Analogue Scale for Anxiety-Revised and school refusal across anxiety profiles」
Aitana Fernández-Sogorb, Cándido J. Inglés, Ricardo Sanmartín, Carolina Gonzálvez, María Vicent, y José Manuel García-Fernánde
International Journal of Clinical and Health Psychology (2018) 18, 264-272
目的:
Visual Analogue Scale for Anxiety-Revised (VAA-R)と呼ばれる、不安に関する尺度の信頼性を確かめること、そして、不安障害と不登校の関係性を分析すること。
方法:
スペインの小学生911名に、VAA-Rを回答してもらう。また、School Refusal Assessment Scale-Revised for Children (SRAS-R-C)とよばれる登校拒否評価尺度にも回答してもらう。
結果:
VAA-Rで得られた結果は、先行研究と同様の結果であったため、信頼性の高いものであると判断された。
また、登校拒否のタイプは複数存在するが、不安障害におけるパターンによって、およぼす影響は異なっていた。
虎太郎所感:
不登校の原因は多様であるがゆえに、単一の方法だけでは解決できません。しかしながら、個々の生徒にあった解決法をそれぞれ独自に作り上げることのコストは、教員にとって大きなものだと考えられます。このような問題点が、登校拒否の解決の難しい点なのだなと、改めて実感しました。
~~(=^・・^=)~~
本日の発表者の方々は、レジュメやパワポの作り方が上手で、とても見やすかったです。
お疲れ様でした。